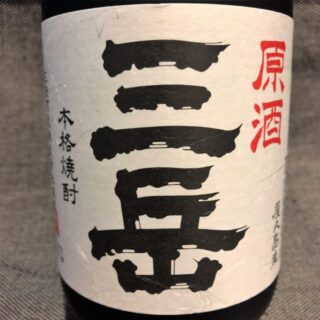2019年5月、屋久島にある三岳酒造へ見学に行きました。
1)一般見学不可
一般見学不可の三岳酒造さんに今回特別に関係者として見学させていただきました。工場内は全て撮影不可の為、写真はありません。
※一般の方が訪問されても見学は出来ません。
※三岳酒造での試飲、販売も一切行っていません。理由は下記で。

2)離島ならではのコスト高!
5月中旬過ぎに伺いましたがまだ仕込みをされていました。今シーズン最後の仕込みだとのことで見学できて本当に良かったです。
原料のサツマイモは屋久島産と鹿児島本土からと混ざっているそうです。屋久島産だけでは生産量が足りないので、鹿児島本土から芋を輸送してくるのでコストがかかって大変なのだそう。
麹をつけるお米はタイ米を使用。ラベルにも記載があります。日本米に変えて作ってみたのだが、やはり三岳にはタイ米が合うので戻したそうです。
タンクの中もしっかり見学しました。酵母とサツマイモを発酵させる段階で対流が発生し自動で激しく動いたり止まったりする酵母の働きを目の当たりにしました。動画でお伝えできないのが残念。対流の発生と共に芋のよい香りが漂います。
水はもちろん屋久島の豊かな自然が育む超軟水。この水があったからこそ三岳ができたと先代の社長さんは常々おっしゃっていたとのこと。

3)売れない時代と地元愛
もともと屋久島の人々は白波という焼酎を飲んでいたそうです。三岳を発売した当初は軽トラに乗せた焼酎が一本も売れずそのまま帰ってきたこともあったそうな。
それがだんだん地元の人に愛されるようになった頃、宮之浦岳・永田岳・黒味岳の三山から命名した三岳焼酎に対して愛子岳地区から愛子焼酎の生産委託があり、その直後に敬宮愛子内親王がお生まれになった事もあって全国に三岳酒造の名が広まったそうです。
全国に名が知れわたると地元でも三岳焼酎が手に入らなくなり先代の社長さんは非常に気を揉まれたそうです。地元の支えがあってここまで来たのに地元の方の手に入らない焼酎ではいけないと。
しかし焼酎製造の工程では必ず芋のカスという廃棄物が出ます。生産量を増やすと芋のカスも増え、狭い島内では引き取り手がありません。生産量が増やせずますます入手困難な焼酎になる日々が続いたそうです。
そんな時、芋のカスを使ったバイオマスエネルギーに目をつけ、政府の環境エネルギー対策の補助制度も活用し大幅に設備投資を行い現在は安定的な生産ができるようになったとのことでした。
工場の外には大きなバイオエネルギー施設がありました。
地元が大切。まだまだ日本全国にも三岳がいきわたっていないので海外には出さないとの方針で、輸出に必要な成分表提出依頼も断っているそうです。
また、三岳酒造を訪問しても試飲や販売も行っていません。地元の酒屋さんに少しでも利益になるように、酒屋さんからお求め下さいとのことでした。
離島ならではの苦労を乗り越え、売れない時代を支えた地元を大切にする精神が先代社長から引き継がれています。
<この蔵の焼酎>詳細はClick !